藤崎翔「逆転美人」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は祝日でクリニックは休診です。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。
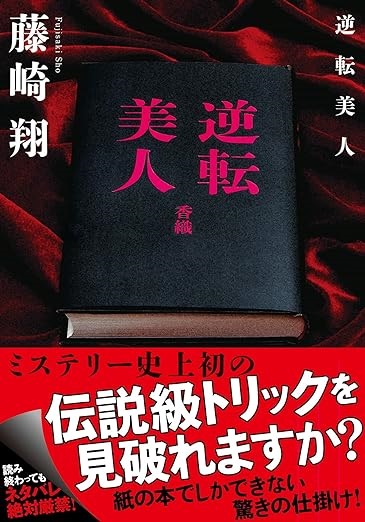
藤崎翔さんによる技巧的なミステリーで、
「世界でいちばん透き通った物語」を読んだ時に、
似た傾向の作品として紹介されていたので、
どんなものだろう、
と思って読んでみたものです。
帯にも、
「ミステリー史上初の伝説級トリックを見破れますか?」
と仰々しいことが書かれていますし、
予備知識があると良くないのではないかしらと思ったのですが、
格別そうしたことはなく読むことが出来ました。
ただ、ネットで「逆転美人」と検索すると、
ネタバレのキーワードが出て来るので、
これは本当に嫌な時代になったな、
というように感じました。
ご興味のある方には一読の価値はあるので、
是非お読み頂きたいのですが、
くれぐれも題名のキーワード検索などはしないようにして下さい。
ガッカリします。
それからちょっと読むのに忍耐が必要で、
前半が湊かなえさんや桐野夏生さんの、
イヤミスの模倣みたいになっているんですね。
これは意図的にそうしたスタイルにしているのですが、
湊さんや桐野さんほど上手くはないので、
それを延々読まされるとうんざりしてしまうのですが、
ここはすいません、忍耐で乗り切って下さい。
勿論それだけの小説ではなく、本質は後半にあるからです。
これはもうミステリー好きのための小説なので、
普通小説のお好きな方にはあまりお勧めは出来ません。
現実の事件をモチーフにした、
かなり深い考察があり、
ルッキズムについての考察もあって、
単純に技巧的なミステリーを書きたいという訳ではなくて、
かなり現代と格闘したいという思いがあって、
書かれた労作だと思うのですが、
普通の小説の好きな方には、
「それならもっとストレートに書いた方がいいのに」
という感想を持ってしまうと思うからです。
たとえば、佐藤正午さんの「身の上話」という小説があるでしょ。
内容的にはかなり似ている部分があるんですね。
人生の有為転変の不思議さであるとか、
「悪」の描き方みたいなものですね。
でも、「身の上話」は普通の小説好きに、
興奮と感銘を与える小説だと思いますが、
この「逆転美人」はそうではないですよね。
そこがこうした小説の弱点ではあるんですね。
本来は技巧に徹した方が良いのですが、
作者としては技巧だけの小説にはしたくない、
という思いも当然あるので、
テーマ的な部分をより膨らませたくなり、
それが全体のバランスを欠く結果になってしまうような気がします。
でも、そこが微笑ましくも感じられ、
僕自身は嫌いではありません。
この小説はスタイルは古典的で、
最初に手記があるという、
ニコラス・ブレイクの「野獣死すべし」のパターンですね。
あの小説は高校生の時に読んで、
結構興奮したことを覚えています。
傑作ですが、何度読んでも、
少し辻褄が合わないような感じがあるんですね。
そこに他の幾つかのミステリーの要素を取り込んで、
メタフィクション的に1つの本の形に全体を落とし込んでいます。
相当苦労して書かれたことの分かる作品で、
少し詰め込み過ぎかなという感じはしますが、
ミステリー好きには一度は読んで損はない力作だと思います。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は祝日でクリニックは休診です。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。
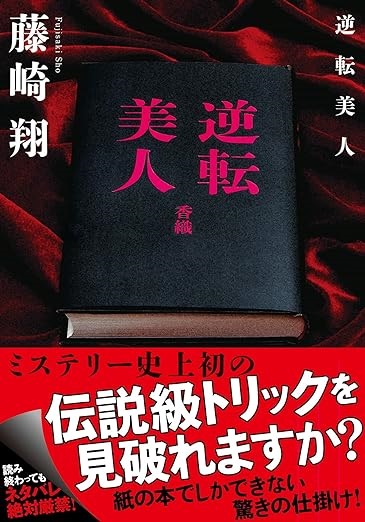
藤崎翔さんによる技巧的なミステリーで、
「世界でいちばん透き通った物語」を読んだ時に、
似た傾向の作品として紹介されていたので、
どんなものだろう、
と思って読んでみたものです。
帯にも、
「ミステリー史上初の伝説級トリックを見破れますか?」
と仰々しいことが書かれていますし、
予備知識があると良くないのではないかしらと思ったのですが、
格別そうしたことはなく読むことが出来ました。
ただ、ネットで「逆転美人」と検索すると、
ネタバレのキーワードが出て来るので、
これは本当に嫌な時代になったな、
というように感じました。
ご興味のある方には一読の価値はあるので、
是非お読み頂きたいのですが、
くれぐれも題名のキーワード検索などはしないようにして下さい。
ガッカリします。
それからちょっと読むのに忍耐が必要で、
前半が湊かなえさんや桐野夏生さんの、
イヤミスの模倣みたいになっているんですね。
これは意図的にそうしたスタイルにしているのですが、
湊さんや桐野さんほど上手くはないので、
それを延々読まされるとうんざりしてしまうのですが、
ここはすいません、忍耐で乗り切って下さい。
勿論それだけの小説ではなく、本質は後半にあるからです。
これはもうミステリー好きのための小説なので、
普通小説のお好きな方にはあまりお勧めは出来ません。
現実の事件をモチーフにした、
かなり深い考察があり、
ルッキズムについての考察もあって、
単純に技巧的なミステリーを書きたいという訳ではなくて、
かなり現代と格闘したいという思いがあって、
書かれた労作だと思うのですが、
普通の小説の好きな方には、
「それならもっとストレートに書いた方がいいのに」
という感想を持ってしまうと思うからです。
たとえば、佐藤正午さんの「身の上話」という小説があるでしょ。
内容的にはかなり似ている部分があるんですね。
人生の有為転変の不思議さであるとか、
「悪」の描き方みたいなものですね。
でも、「身の上話」は普通の小説好きに、
興奮と感銘を与える小説だと思いますが、
この「逆転美人」はそうではないですよね。
そこがこうした小説の弱点ではあるんですね。
本来は技巧に徹した方が良いのですが、
作者としては技巧だけの小説にはしたくない、
という思いも当然あるので、
テーマ的な部分をより膨らませたくなり、
それが全体のバランスを欠く結果になってしまうような気がします。
でも、そこが微笑ましくも感じられ、
僕自身は嫌いではありません。
この小説はスタイルは古典的で、
最初に手記があるという、
ニコラス・ブレイクの「野獣死すべし」のパターンですね。
あの小説は高校生の時に読んで、
結構興奮したことを覚えています。
傑作ですが、何度読んでも、
少し辻褄が合わないような感じがあるんですね。
そこに他の幾つかのミステリーの要素を取り込んで、
メタフィクション的に1つの本の形に全体を落とし込んでいます。
相当苦労して書かれたことの分かる作品で、
少し詰め込み過ぎかなという感じはしますが、
ミステリー好きには一度は読んで損はない力作だと思います。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
「medium 霊媒探偵城塚翡翠」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は祝日でクリニックは休診です。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。

相沢沙呼さんによる2019年刊行のミステリーで、
ミステリーマニアには非常に評価が高かった作品です。
少し前に読んでみました。
霊媒の美少女と推理作家がタッグを組んで、
色々なタイプの事件を解決するという、
オムニバス形式のミステリーで、
それが中途から意外な展開を見せ、
凝りに凝った解決編に至ります。
確かに凝っているのですが、
全ての事件を2通りの方法で論理的に解決する、
というものなので、
マニア以外には、
「それがどうした、面倒くさいな」という感じがしてしまうのと、
犯人はロジックは異なっていても結局は一緒なので、
何か詰まらなく感じてしまうのです。
これ、予備校で有名教師が数学の問題を、
沢山の解法で解いて、
それに感心するのに似ていますよね。
そういうのを面白いと思う人には向いている作品です。
キャラクターが薄っぺらで一昔前の漫画レベルなのと、
一応意外な犯人として想定されているのが、
結構丸わかりなのも、
マニア以外の一般の読者の印象を悪くしていると思います。
マニアにとっては凝りに凝った趣向と、
エレガントな解法があればそれでいいんですよね。
その意味では傑作なのだと思います。
個人的にはこうした凝り方はあまりツボではありませんでした。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は祝日でクリニックは休診です。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。

相沢沙呼さんによる2019年刊行のミステリーで、
ミステリーマニアには非常に評価が高かった作品です。
少し前に読んでみました。
霊媒の美少女と推理作家がタッグを組んで、
色々なタイプの事件を解決するという、
オムニバス形式のミステリーで、
それが中途から意外な展開を見せ、
凝りに凝った解決編に至ります。
確かに凝っているのですが、
全ての事件を2通りの方法で論理的に解決する、
というものなので、
マニア以外には、
「それがどうした、面倒くさいな」という感じがしてしまうのと、
犯人はロジックは異なっていても結局は一緒なので、
何か詰まらなく感じてしまうのです。
これ、予備校で有名教師が数学の問題を、
沢山の解法で解いて、
それに感心するのに似ていますよね。
そういうのを面白いと思う人には向いている作品です。
キャラクターが薄っぺらで一昔前の漫画レベルなのと、
一応意外な犯人として想定されているのが、
結構丸わかりなのも、
マニア以外の一般の読者の印象を悪くしていると思います。
マニアにとっては凝りに凝った趣向と、
エレガントな解法があればそれでいいんですよね。
その意味では傑作なのだと思います。
個人的にはこうした凝り方はあまりツボではありませんでした。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
東野圭吾「危険なビーナス」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は日曜日でクリニックは休診ですが、
終日レセプト作業の予定です。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。
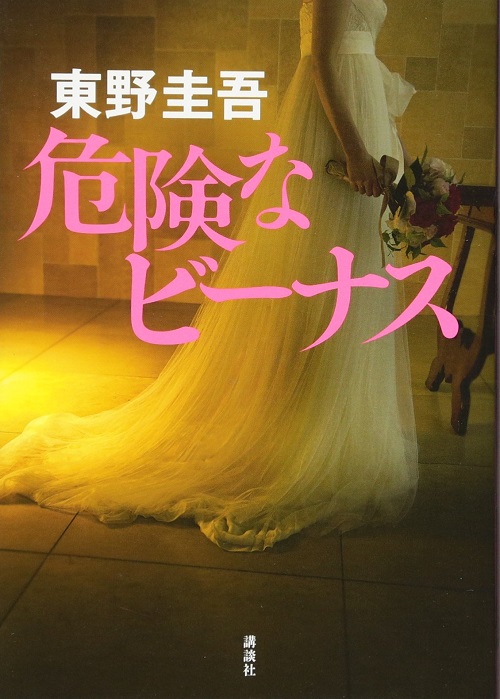
東野圭吾さんの比較的最近刊行されたミステリーで、
今テレビドラマ化されているものの原作です。
東野圭吾さんの作品は、
「鳥人計画」や「魔球」の頃から、
比較的多く読んでいる方ですが、
最近は意識的に軽いタッチのライトノベル的なものと、
本格的な小説とに、
分けて執筆をされているように思います。
「秘密」や「手紙」、「白夜行」などは、
文学作品としても優れたものだと思いますが、
本格ミステリーについても、
軽いタッチのものから、
重厚なもの、
ミステリーの限界に挑戦したようなマニアックなものなど、
多くの振り幅があります。
湯川博士のシリーズなどは、
開始当初は他の作者の有名シリーズの、
明らかな二番煎じという感じで、
あまり高いレベルを目指したものではなかったように感じましたが、
「容疑者Xの献身」の辺りから作者の本気が見え始め、
今では代表作の1つと言って良い、
本格的な小説の柱の1つに成長しています。
ただ、この「危険なビーナス」については、
「マスカレードホテル」のシリーズと同じように、
肩の凝らない、ミステリー初心者向けの、
ライトノベル的な作風となっています。
トーマの有名な「罠」が、
ベースになっているように感じましたが、
それほど深みのある内容ではなく、
犯人の屈折した造形などは、
さすが東野圭吾という感じも仄見えるのですが、
意図的に古いタイプのミステリーに着地しています。
私見では東野さんはかなり意地悪で、
人間観察には独特の冷たさのようなものがあり、
医療や医者は基本的に嫌っているようです。
この作品もそうした点は現れていて、
医療者としては読んでいてつらい感じもあります。
全体的にはほのぼのした軽いタッチですが、
ラストでは主人公の運命を、
ちょっと突き放したように見ている感じがするのは、
東野さんのダークサイドがのぞいている、
という気がします。
これを読むと、
かなりスカスカの内容に、
とても連続ドラマにはならないように感じますが、
ドラマを見てみると、
それがどうして、
ちょっとした人間の駆け引きを引き延ばして、
結構ドラマとしては成立しているのに驚きます。
何もないものを、
何かあるが如くに引き伸ばし続けるのが、
なるほど連続ドラマの極意なのだなあと、
妙に感心しました。
東野さんの作品としては、
それほど気合の入ったものではありません。
コアなファンのみにお勧めです。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
追伸;レセプトが終わりません(泣)。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は日曜日でクリニックは休診ですが、
終日レセプト作業の予定です。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。
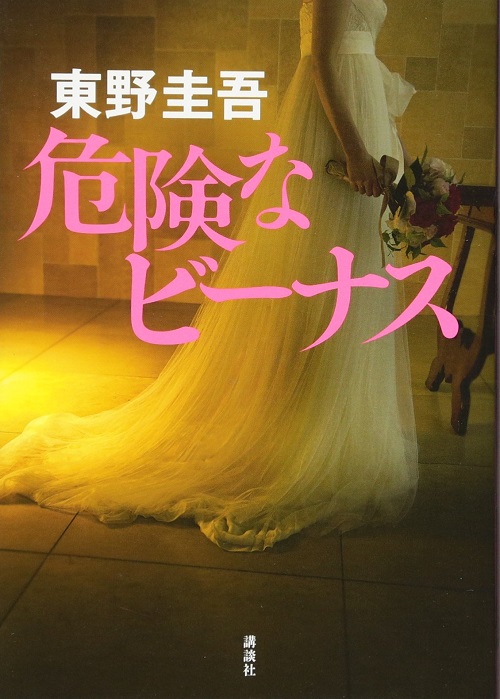
東野圭吾さんの比較的最近刊行されたミステリーで、
今テレビドラマ化されているものの原作です。
東野圭吾さんの作品は、
「鳥人計画」や「魔球」の頃から、
比較的多く読んでいる方ですが、
最近は意識的に軽いタッチのライトノベル的なものと、
本格的な小説とに、
分けて執筆をされているように思います。
「秘密」や「手紙」、「白夜行」などは、
文学作品としても優れたものだと思いますが、
本格ミステリーについても、
軽いタッチのものから、
重厚なもの、
ミステリーの限界に挑戦したようなマニアックなものなど、
多くの振り幅があります。
湯川博士のシリーズなどは、
開始当初は他の作者の有名シリーズの、
明らかな二番煎じという感じで、
あまり高いレベルを目指したものではなかったように感じましたが、
「容疑者Xの献身」の辺りから作者の本気が見え始め、
今では代表作の1つと言って良い、
本格的な小説の柱の1つに成長しています。
ただ、この「危険なビーナス」については、
「マスカレードホテル」のシリーズと同じように、
肩の凝らない、ミステリー初心者向けの、
ライトノベル的な作風となっています。
トーマの有名な「罠」が、
ベースになっているように感じましたが、
それほど深みのある内容ではなく、
犯人の屈折した造形などは、
さすが東野圭吾という感じも仄見えるのですが、
意図的に古いタイプのミステリーに着地しています。
私見では東野さんはかなり意地悪で、
人間観察には独特の冷たさのようなものがあり、
医療や医者は基本的に嫌っているようです。
この作品もそうした点は現れていて、
医療者としては読んでいてつらい感じもあります。
全体的にはほのぼのした軽いタッチですが、
ラストでは主人公の運命を、
ちょっと突き放したように見ている感じがするのは、
東野さんのダークサイドがのぞいている、
という気がします。
これを読むと、
かなりスカスカの内容に、
とても連続ドラマにはならないように感じますが、
ドラマを見てみると、
それがどうして、
ちょっとした人間の駆け引きを引き延ばして、
結構ドラマとしては成立しているのに驚きます。
何もないものを、
何かあるが如くに引き伸ばし続けるのが、
なるほど連続ドラマの極意なのだなあと、
妙に感心しました。
東野さんの作品としては、
それほど気合の入ったものではありません。
コアなファンのみにお勧めです。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
追伸;レセプトが終わりません(泣)。
七河迦南「アルバトロスは羽ばたかない」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は祝日でクリニックは休診です。
明日からはいつも通りの診療になります。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。
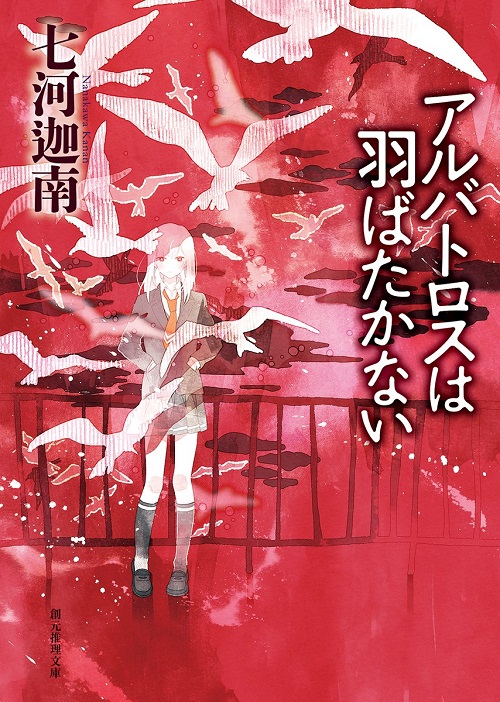
ミステリーは一時期は取り憑かれたように読んでいて、
ミステリーと心中するような感じすらあったのですが、
今では時々読むというくらいになっています。
この作品は最近読んで中段までは結構興奮しました。
ただ、最後まで読むと、
ちょっとどうかな、と感じました。
そもそも物語として成立していないように思うのですが、
多くの方が絶賛されているので、
僕の見方が間違っているのかしら、
と自信がなくなります。
以下、ネタバレはしませんが、
何となく内容が分かるような表現はありますので、
未読の方はご注意下さい。
養護施設の教員を探偵役にしたシリーズもので、
何より文章が抜群に上手くて、
品がありますよね。
新人の2作目とは思えない完成度です。
文化祭の当日に校舎の屋上から転落した、
という事件があり、
それを調査するパートと、
過去の関連するエピソードが交錯するように展開され、
過去のエピソードは、
それ自体が独立したミステリー短編のようになっています。
ただ、謎はあるのですが、
殺人などは起こりません。
事件と言って良い大掛かりなものも1つあるのですが、
後は「日常や心理の謎」というタイプのものです。
短編エピソードもなかなか巧みなのですね。
伏線の張り巡らし方がなかなかで、
マニア向け本格のような、
論理で頭が痛くなるようなところはありません。
「あっ。何となく読んでても違和感があったけど、
実はそうだったのね。上手いね」
という感じです。
そこから次第に、
本筋の事件にフォーカスが当たってゆきます。
ただ、肝心の事件というのが、
屋上から落ちた、というだけのものなので、
登場人物達が持っているほど、
こちらは関心が持てない、というきらいはあります。
そして、ついに事件の真相が分かるということになり、
興奮しながら読み進めると、
「えっ?」
ということになります。
読んだ瞬間は、ビックリしましたし、
凄いな、と思いました。
ただ、良く考えてみると、
それじゃ設定として成立しないのじゃないか、
と思いました。
だって、それが真相だと言うのなら、
それはそもそも事件にならないでしょ。
違うのかなあ、と思って何度か読み返しましたが、
その感想は変わりませんでした。
これをミステリーとして評価するのは、
ちょっとどうかな、と思います。
ただ、それを言い出せば、
中井英夫さんの「虚無への供物」とか、
デタラメで全く辻褄なんて合わないですよね。
それでも、やっぱりあれは傑作なので、
そうしたことで考えれば、
この作品も小説としては充分魅力的なので、
それでいいのかな、とも思いました。
良いミステリーに出逢うというのも、
僕にとってはかけがえのない経験の1つで、
これからも合間を見て、
その世界には浸りたいと思います。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は祝日でクリニックは休診です。
明日からはいつも通りの診療になります。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。
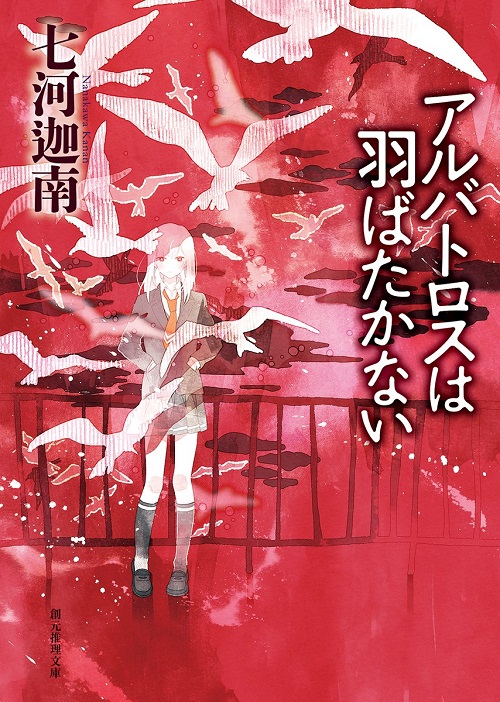
ミステリーは一時期は取り憑かれたように読んでいて、
ミステリーと心中するような感じすらあったのですが、
今では時々読むというくらいになっています。
この作品は最近読んで中段までは結構興奮しました。
ただ、最後まで読むと、
ちょっとどうかな、と感じました。
そもそも物語として成立していないように思うのですが、
多くの方が絶賛されているので、
僕の見方が間違っているのかしら、
と自信がなくなります。
以下、ネタバレはしませんが、
何となく内容が分かるような表現はありますので、
未読の方はご注意下さい。
養護施設の教員を探偵役にしたシリーズもので、
何より文章が抜群に上手くて、
品がありますよね。
新人の2作目とは思えない完成度です。
文化祭の当日に校舎の屋上から転落した、
という事件があり、
それを調査するパートと、
過去の関連するエピソードが交錯するように展開され、
過去のエピソードは、
それ自体が独立したミステリー短編のようになっています。
ただ、謎はあるのですが、
殺人などは起こりません。
事件と言って良い大掛かりなものも1つあるのですが、
後は「日常や心理の謎」というタイプのものです。
短編エピソードもなかなか巧みなのですね。
伏線の張り巡らし方がなかなかで、
マニア向け本格のような、
論理で頭が痛くなるようなところはありません。
「あっ。何となく読んでても違和感があったけど、
実はそうだったのね。上手いね」
という感じです。
そこから次第に、
本筋の事件にフォーカスが当たってゆきます。
ただ、肝心の事件というのが、
屋上から落ちた、というだけのものなので、
登場人物達が持っているほど、
こちらは関心が持てない、というきらいはあります。
そして、ついに事件の真相が分かるということになり、
興奮しながら読み進めると、
「えっ?」
ということになります。
読んだ瞬間は、ビックリしましたし、
凄いな、と思いました。
ただ、良く考えてみると、
それじゃ設定として成立しないのじゃないか、
と思いました。
だって、それが真相だと言うのなら、
それはそもそも事件にならないでしょ。
違うのかなあ、と思って何度か読み返しましたが、
その感想は変わりませんでした。
これをミステリーとして評価するのは、
ちょっとどうかな、と思います。
ただ、それを言い出せば、
中井英夫さんの「虚無への供物」とか、
デタラメで全く辻褄なんて合わないですよね。
それでも、やっぱりあれは傑作なので、
そうしたことで考えれば、
この作品も小説としては充分魅力的なので、
それでいいのかな、とも思いました。
良いミステリーに出逢うというのも、
僕にとってはかけがえのない経験の1つで、
これからも合間を見て、
その世界には浸りたいと思います。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
横溝正史「獄門島」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で午前午後とも中村医師が外来を担当する予定です。
今日は土曜日なので趣味の話題です。
今日はこちら。

横溝正史の代表作「獄門島」です。
日本の本格ミステリー史上に残る名作ですが、
作品のポイントとなる部分に、
放送などには適さないとされる表現がある関係で、
これまで何度も映画やドラマ化はされながら、
オリジナルに忠実に映像化されたことが殆どない、
という曰く付きの作品でもあります。
この作品との出会いは小学校の低学年の頃で、
何年生くらいだったのかしら、
ちょっと覚えていないのですが、
それほど上の学年ではなかったことは確かです。
母親に夜色々な小説の読み聞かせをしてもらったのですが、
そのラインナップがかなりマニアックで、
最初は子供向けの読み物から始まって、
そのうちに横溝正史のミステリーや、
「西遊記」の原典からの完訳全巻などになりました。
勿論全部オリジナルで子供向けのリライトではありません。
横溝正史の長編ミステリーなら1週間くらい、
「西遊記」は多分1か月以上かかったと思います。
横溝正史ものはその時に、
「獄門島」、「八つ墓村」、「女王蜂」、「犬神家の一族」を、
読み聞かせてもらいました。
子供の頃にそれも耳から読んでいるので、
とてもとても強い印象がありましたし、
今でもこの4つの作品については、
そのイメージをありありと思い描くことが出来ます。
矢張り当時は「八つ墓村」が印象強烈でした。
ただ、今思うとあれは江戸川乱歩の、
「孤島の鬼」辺りの影響が強いですよね。
もともと横溝正史は編集者で、
乱歩に影響されて作品を書き始めて、
戦前のものは乱歩のパクリみたいなものが多かったんですよね、
それが戦後になって名探偵金田一耕助を登場させると、
その作風はカーをお手本にした、
本格ミステリーに変化したのです。
ただ、戦後の作品にも乱歩趣味のものがあり、
「八つ墓村」はその代表と言って良いのだと思います。
「獄門島」はそれに比べると印象は薄かったのですが、
他の作品にはない風格というか、
唯一無二という感じがあって、
子供心にもワクワクしました。
カーの幾つかの作品をお手本にしているのですが、
その変え方というか、アレンジの仕方も絶妙ですし、
犯人の造形も非常に印象的に描かれています。
綾辻行人さん以降の新本格のミステリーの系譜も、
矢張りこの作品なしでは生まれえなかった、
と言っていいような感じがありますね。
ミステリーとしての完成度についてはどうなのかな、
何度も読み返しているんですが、
最初の殺人は素晴らしいですよね。
2番目の殺人もとても魅力的なのですが、
少し意味不明という感じもあります。
トリックはとてもとても素敵なのですが、
そんなことしてもなあ、
という感じがあるのですね。
3番目の殺人は明らかに弱いですね。
また、殺人の動機がね、
とても有名なミステリーを下敷きにしている、
というのは分かるのです。
ただ、矢張りすっきりはしていないですね。
色々と補足や言い訳がついてしまっているので、
素直に腑に落ちない、という感じがあるのです。
その意味でミステリーの骨格としては、
「本陣殺人事件」の方が上とは思います。
今読むとラストが読めてしまう、というところはあるのですが、
動機も含めてとても完成度は高いですよね。
ただ、ちょっと短いですし、
乱歩タッチが抜けていないような仰々しさがあるので、
作品の風格と言う面では、
「獄門島」の方がはるかに上です。
そんな傑作ミステリーですが、
映像化ではあまり良い結果になっていません。
原作刊行から間もない1949年に、
松田定次監督により映画化されていますが、
これは片岡千恵蔵の多羅尾坂内シリーズの系譜にあるもので、
原作の設定は借りながら、犯人などは全く別になっている怪奇スリラーです。
このシリーズは横溝作品をかたっぱしから映画化しているのですが、
そのほぼ全てで犯人は原作と違っています。
これはまあ、1つの見識で、
ミステリーファンとしてはむしろ好ましく感じます。
その後角川書店が仕掛けた、
横溝作品リバイバルというのが1970代にあって、
角川映画の「犬神家の一族」が大ヒットしたので、
同じ市川崑監督が1977年に映画化しました。
「犬神家の一族」は僕も大好きですが、
横溝ミステリーがほぼ原作通りに映画化された、
史上初めてのケースと言って良い画期的映画でした。
ただ、一番良いところで佐清の仮面が透けて見えるところがあるでしょ。
あれはかなり痛恨のミスカットですね。
誰か気が付かなかったのかしら。
それで1977年の映画「獄門島」はとても期待して、
封切りに渋谷の映画館で観たのですが、
おやおや、という感じで正直ガッカリしました。
これね、犯人を変えているんですよね。
それは予告でもそう謳っていましたし、
松田定次方式と考えれば良いと思うのですが、
実際にはほとんど同じストーリーであるのに、
その一部だけを強引に変えて、
「犯人を変えた」と言っているんですね。
これじゃただ原作を詰まらなくしただけでしょ。
駄目だこりゃ、という感じでした。
これね、3つの殺人に3つのトリック、
というのがいいんですよ。
それを崩しちゃ駄目なのに、
映像化すると絶対変えちゃうんですよね。
確かに原作も3つ目のトリックが弱いので、
気持ちは分かるのですが、
でも変えちゃ駄目なんだよ。
ただ、原作そのままの部分は、
なかなかいいんですよね。
大原麗子さんも抜群にいいし。
原作の戦後の無常観のようなものも、
良く出ていたと思います。
それでこの映画は結構何度も観ています。
テレビでちょうどいいという感じ。
ただ、原作を変えた部分はまどろっこしくて、
イライラしてしまいます。
同年に古谷一行が主役のテレビシリーズで、
「獄門島」が放映されましたが、
これは原作の設定が大きく変わっていて、
放映に適さないとされる用語や設定が、
バッサリなくなっていました。
これなら、やらない方がましじゃん。
とても残念です。
その後何度かテレビドラマになりましたが、
例によって設定はガタガタに変えられていたので、
遺族の方もこれなら映像化にOKを出さない方がいいのに、
と無念の思いがありました。
2016年にBSで制作されたものは、
かなり原作に近く、用語もそのままであったようですが、
これは観ていません。
「獄門島」は今読んでも、
新鮮な驚きと戦後の喪失感のようなものを感じられる、
日本屈指の名作ミステリーだと思いますが、
テレビの情報などがあると、
予備知識があって楽しめない方が多いと思うので、
その点は非常に残念です。
ウィキペディアにも、
ネタバレとかの記載なく、
ストーリーが最後まで書かれていますし、
今の情報過多は本当に嫌になります。
私見ですが、
戦中戦後くらいの設定のドラマは、
もう絶対にその時の感触では再現できないので、
しばらく作るのは止めてもらった方が良いように思います。
これがもう100年くらいすれば、
ファンタジーとして成立するので良いのですが、
今は作るだけ嘘の上塗りになるだけなので、
昔の作品を見る機会を増やして頂いた方が、
よほど建設的であるように思います。
今日はすいません。
そんな感じでつれづれなるままに雑感でした。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で午前午後とも中村医師が外来を担当する予定です。
今日は土曜日なので趣味の話題です。
今日はこちら。

横溝正史の代表作「獄門島」です。
日本の本格ミステリー史上に残る名作ですが、
作品のポイントとなる部分に、
放送などには適さないとされる表現がある関係で、
これまで何度も映画やドラマ化はされながら、
オリジナルに忠実に映像化されたことが殆どない、
という曰く付きの作品でもあります。
この作品との出会いは小学校の低学年の頃で、
何年生くらいだったのかしら、
ちょっと覚えていないのですが、
それほど上の学年ではなかったことは確かです。
母親に夜色々な小説の読み聞かせをしてもらったのですが、
そのラインナップがかなりマニアックで、
最初は子供向けの読み物から始まって、
そのうちに横溝正史のミステリーや、
「西遊記」の原典からの完訳全巻などになりました。
勿論全部オリジナルで子供向けのリライトではありません。
横溝正史の長編ミステリーなら1週間くらい、
「西遊記」は多分1か月以上かかったと思います。
横溝正史ものはその時に、
「獄門島」、「八つ墓村」、「女王蜂」、「犬神家の一族」を、
読み聞かせてもらいました。
子供の頃にそれも耳から読んでいるので、
とてもとても強い印象がありましたし、
今でもこの4つの作品については、
そのイメージをありありと思い描くことが出来ます。
矢張り当時は「八つ墓村」が印象強烈でした。
ただ、今思うとあれは江戸川乱歩の、
「孤島の鬼」辺りの影響が強いですよね。
もともと横溝正史は編集者で、
乱歩に影響されて作品を書き始めて、
戦前のものは乱歩のパクリみたいなものが多かったんですよね、
それが戦後になって名探偵金田一耕助を登場させると、
その作風はカーをお手本にした、
本格ミステリーに変化したのです。
ただ、戦後の作品にも乱歩趣味のものがあり、
「八つ墓村」はその代表と言って良いのだと思います。
「獄門島」はそれに比べると印象は薄かったのですが、
他の作品にはない風格というか、
唯一無二という感じがあって、
子供心にもワクワクしました。
カーの幾つかの作品をお手本にしているのですが、
その変え方というか、アレンジの仕方も絶妙ですし、
犯人の造形も非常に印象的に描かれています。
綾辻行人さん以降の新本格のミステリーの系譜も、
矢張りこの作品なしでは生まれえなかった、
と言っていいような感じがありますね。
ミステリーとしての完成度についてはどうなのかな、
何度も読み返しているんですが、
最初の殺人は素晴らしいですよね。
2番目の殺人もとても魅力的なのですが、
少し意味不明という感じもあります。
トリックはとてもとても素敵なのですが、
そんなことしてもなあ、
という感じがあるのですね。
3番目の殺人は明らかに弱いですね。
また、殺人の動機がね、
とても有名なミステリーを下敷きにしている、
というのは分かるのです。
ただ、矢張りすっきりはしていないですね。
色々と補足や言い訳がついてしまっているので、
素直に腑に落ちない、という感じがあるのです。
その意味でミステリーの骨格としては、
「本陣殺人事件」の方が上とは思います。
今読むとラストが読めてしまう、というところはあるのですが、
動機も含めてとても完成度は高いですよね。
ただ、ちょっと短いですし、
乱歩タッチが抜けていないような仰々しさがあるので、
作品の風格と言う面では、
「獄門島」の方がはるかに上です。
そんな傑作ミステリーですが、
映像化ではあまり良い結果になっていません。
原作刊行から間もない1949年に、
松田定次監督により映画化されていますが、
これは片岡千恵蔵の多羅尾坂内シリーズの系譜にあるもので、
原作の設定は借りながら、犯人などは全く別になっている怪奇スリラーです。
このシリーズは横溝作品をかたっぱしから映画化しているのですが、
そのほぼ全てで犯人は原作と違っています。
これはまあ、1つの見識で、
ミステリーファンとしてはむしろ好ましく感じます。
その後角川書店が仕掛けた、
横溝作品リバイバルというのが1970代にあって、
角川映画の「犬神家の一族」が大ヒットしたので、
同じ市川崑監督が1977年に映画化しました。
「犬神家の一族」は僕も大好きですが、
横溝ミステリーがほぼ原作通りに映画化された、
史上初めてのケースと言って良い画期的映画でした。
ただ、一番良いところで佐清の仮面が透けて見えるところがあるでしょ。
あれはかなり痛恨のミスカットですね。
誰か気が付かなかったのかしら。
それで1977年の映画「獄門島」はとても期待して、
封切りに渋谷の映画館で観たのですが、
おやおや、という感じで正直ガッカリしました。
これね、犯人を変えているんですよね。
それは予告でもそう謳っていましたし、
松田定次方式と考えれば良いと思うのですが、
実際にはほとんど同じストーリーであるのに、
その一部だけを強引に変えて、
「犯人を変えた」と言っているんですね。
これじゃただ原作を詰まらなくしただけでしょ。
駄目だこりゃ、という感じでした。
これね、3つの殺人に3つのトリック、
というのがいいんですよ。
それを崩しちゃ駄目なのに、
映像化すると絶対変えちゃうんですよね。
確かに原作も3つ目のトリックが弱いので、
気持ちは分かるのですが、
でも変えちゃ駄目なんだよ。
ただ、原作そのままの部分は、
なかなかいいんですよね。
大原麗子さんも抜群にいいし。
原作の戦後の無常観のようなものも、
良く出ていたと思います。
それでこの映画は結構何度も観ています。
テレビでちょうどいいという感じ。
ただ、原作を変えた部分はまどろっこしくて、
イライラしてしまいます。
同年に古谷一行が主役のテレビシリーズで、
「獄門島」が放映されましたが、
これは原作の設定が大きく変わっていて、
放映に適さないとされる用語や設定が、
バッサリなくなっていました。
これなら、やらない方がましじゃん。
とても残念です。
その後何度かテレビドラマになりましたが、
例によって設定はガタガタに変えられていたので、
遺族の方もこれなら映像化にOKを出さない方がいいのに、
と無念の思いがありました。
2016年にBSで制作されたものは、
かなり原作に近く、用語もそのままであったようですが、
これは観ていません。
「獄門島」は今読んでも、
新鮮な驚きと戦後の喪失感のようなものを感じられる、
日本屈指の名作ミステリーだと思いますが、
テレビの情報などがあると、
予備知識があって楽しめない方が多いと思うので、
その点は非常に残念です。
ウィキペディアにも、
ネタバレとかの記載なく、
ストーリーが最後まで書かれていますし、
今の情報過多は本当に嫌になります。
私見ですが、
戦中戦後くらいの設定のドラマは、
もう絶対にその時の感触では再現できないので、
しばらく作るのは止めてもらった方が良いように思います。
これがもう100年くらいすれば、
ファンタジーとして成立するので良いのですが、
今は作るだけ嘘の上塗りになるだけなので、
昔の作品を見る機会を増やして頂いた方が、
よほど建設的であるように思います。
今日はすいません。
そんな感じでつれづれなるままに雑感でした。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
セオドア・ロスコー「死の相続」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で、
午前午後とも代診となります。
土曜日は趣味の話題です。
今日はこちら。
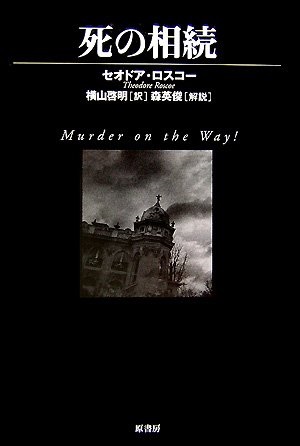
パルプ作家で日本では長く無名であった、
アメリカのセオドア・ロスコーの、
日本唯一の翻訳長編ミステリーです。
これはかなり前に買ったのですが、
長く積読としていました。
今回「屍人荘の殺人」を読み、
そう言えば…と思って読んでみたものです。
これはなかなか面白かったです。
1935年という本格ミステリーの黄金時代に発表されたものですが、
ハイチを舞台として、
農園を経営する資産家が奇怪な遺言状を残して変死し、
そこにアメリカ人の若いカップルが巻き込まれて、
24時間の血で血を洗う惨劇が展開されます。
そこに更に政府転覆を狙う暴動が起こり、
超自然的現象まで起こって、
事件は混沌とした様相を呈します。
この、とても解決しないように思える、
大風呂敷を広げ過ぎたように思える事件が、
ラストには見事に解決するのです。
そのさすがの手際には感心します。
複数の不可能犯罪と密室トリックが含まれていて、
そのトリック自体はやや他愛のないものなのですが、
事件の最も大きな真相と、
トリックが有機的に結び付いているというところに、
この作品の優れた点があります。
正直「屍人荘の殺人」の10倍くらい面白い作品でした。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で、
午前午後とも代診となります。
土曜日は趣味の話題です。
今日はこちら。
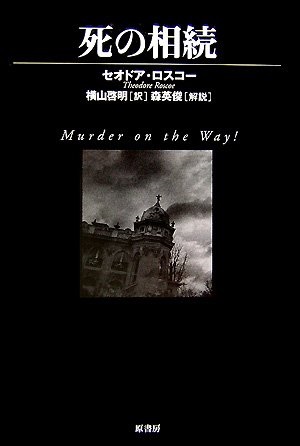
パルプ作家で日本では長く無名であった、
アメリカのセオドア・ロスコーの、
日本唯一の翻訳長編ミステリーです。
これはかなり前に買ったのですが、
長く積読としていました。
今回「屍人荘の殺人」を読み、
そう言えば…と思って読んでみたものです。
これはなかなか面白かったです。
1935年という本格ミステリーの黄金時代に発表されたものですが、
ハイチを舞台として、
農園を経営する資産家が奇怪な遺言状を残して変死し、
そこにアメリカ人の若いカップルが巻き込まれて、
24時間の血で血を洗う惨劇が展開されます。
そこに更に政府転覆を狙う暴動が起こり、
超自然的現象まで起こって、
事件は混沌とした様相を呈します。
この、とても解決しないように思える、
大風呂敷を広げ過ぎたように思える事件が、
ラストには見事に解決するのです。
そのさすがの手際には感心します。
複数の不可能犯罪と密室トリックが含まれていて、
そのトリック自体はやや他愛のないものなのですが、
事件の最も大きな真相と、
トリックが有機的に結び付いているというところに、
この作品の優れた点があります。
正直「屍人荘の殺人」の10倍くらい面白い作品でした。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
今村昌弘「魔眼の匣の殺人」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で、
午前中は中村医師が、
午後2時以降は石原が担当する予定です。
土曜日は趣味の話題です。
今日はこちら。
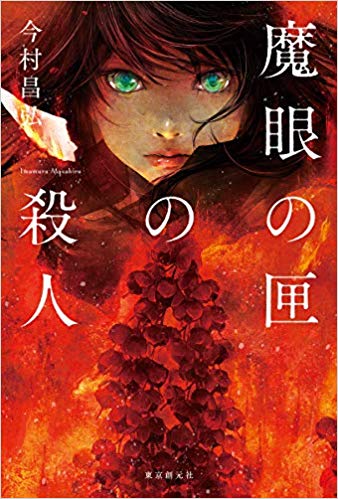
今村昌弘さんの新作ミステリー「魔眼の匣の殺人」を読みました。
ミステリ―は中学から高校の頃が、
一番のめり込んでいた感じで、
早川ミステリの絶版本を求めて、
神保町を何度も彷徨いました。
大学になって新本格と言われる、
外連味のある本格ミステリーが、
猿之助の復活歌舞伎のように復興し、
それが「金田一少年の事件簿」以降、
漫画の世界に広がることで、
その裾野は一気に拡大して今に至っています。
江戸川乱歩の「続幻影城」を読んで、
カーのミステリーの絶版を悲しみ、
早川ミステリ文庫の発刊にワクワクし、
雑誌の「幻影城」で泡坂妻夫さんの短編に驚き、
「匣の中の失楽」の連載を高校1年の孤独な春に、
読みふけったことも今では遠い思い出です。
さて、今村さんのデビュー作の「屍人荘の殺人」は、
2017年のミステリー界の話題をさらったヒット作で、
あるホラーなどにお馴染みの設定と、
クイーン流の犯人絞り込みのロジックの謎解きを、
組み合わせたミステリーです。
雰囲気は新本格などの館ものですが、
ミステリーのロジックとリアルでない設定を同居させた発想は、
アシモフのSFミステリーと同じです。
アシモフの「鋼鉄都市」では、
プログラム上人間を殺せない筈のロボットが、
人間を殺したとしか思えない状況が、
ミステリーとして設定されていたのですが、
それを別のテーマでミステリー化しているのです。
ただ、個人的にはあまり面白く感じませんでした。
もう脳が老化しているので、
犯人絞り込みのロジックの部分が、
ごちゃごちゃとして面倒にしか思えません。
また、超自然的な設定の方が、
館の中のチマチマした殺人より、
間違いなく大きいので、
大きな事件は解決しないのに、
チマチマした殺人のみ解決するというのでは、
本末転倒で安易であるように感じたのです。
今回はその続編ですが、
前作の設定は踏襲しつつ、
今度は「予言」をテーマにしています。
通常のミステリーでは、
予言というのは基本的にトリックなのですが、
今回はトリックとは思えない予言がバンバン出現し、
ははあ、要するにこれもミステリーと超自然のミックスなのね、
ということが分かります。
今回はラストに、
如何にもミステリー的な捻りがあるので、
前作よりミステリーとしての満足感が高いものになっています。
小さなトリックを積み上げる感じは、
クレイトン・ロースンみたいでしたね。
ただ、矢張り大枠にある謎は、
リアルにせよ超自然的にせよ解決はされないので、
モヤモヤする感じが残ることは同じです。
あと、昔流行った、
大きな木の棒が忽然と現れるという、
マジックネタを利用したトリックがあるのですが、
これはさすがにしょぼくてガッカリしました。
多分マジック好きでない方は、
本文を読まれてもなんのことか分からないと思うのですが、
実際にそうしたネタがあるのです。
ただ、これは出現であって消失の仕掛ではないので、
本文を読む限り成立しないと思いました。
こういうのは僕は嫌いです。
そんな訳で今回もあまり乗らなかったのですが、
一部は脳の老化のせいかなあ、と思うところもあるので、
久しぶりに本家のクイーンでも、
じっくり読んでみようかな、
などと思っています。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で、
午前中は中村医師が、
午後2時以降は石原が担当する予定です。
土曜日は趣味の話題です。
今日はこちら。
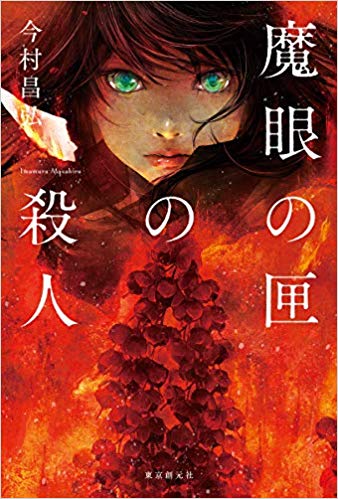
今村昌弘さんの新作ミステリー「魔眼の匣の殺人」を読みました。
ミステリ―は中学から高校の頃が、
一番のめり込んでいた感じで、
早川ミステリの絶版本を求めて、
神保町を何度も彷徨いました。
大学になって新本格と言われる、
外連味のある本格ミステリーが、
猿之助の復活歌舞伎のように復興し、
それが「金田一少年の事件簿」以降、
漫画の世界に広がることで、
その裾野は一気に拡大して今に至っています。
江戸川乱歩の「続幻影城」を読んで、
カーのミステリーの絶版を悲しみ、
早川ミステリ文庫の発刊にワクワクし、
雑誌の「幻影城」で泡坂妻夫さんの短編に驚き、
「匣の中の失楽」の連載を高校1年の孤独な春に、
読みふけったことも今では遠い思い出です。
さて、今村さんのデビュー作の「屍人荘の殺人」は、
2017年のミステリー界の話題をさらったヒット作で、
あるホラーなどにお馴染みの設定と、
クイーン流の犯人絞り込みのロジックの謎解きを、
組み合わせたミステリーです。
雰囲気は新本格などの館ものですが、
ミステリーのロジックとリアルでない設定を同居させた発想は、
アシモフのSFミステリーと同じです。
アシモフの「鋼鉄都市」では、
プログラム上人間を殺せない筈のロボットが、
人間を殺したとしか思えない状況が、
ミステリーとして設定されていたのですが、
それを別のテーマでミステリー化しているのです。
ただ、個人的にはあまり面白く感じませんでした。
もう脳が老化しているので、
犯人絞り込みのロジックの部分が、
ごちゃごちゃとして面倒にしか思えません。
また、超自然的な設定の方が、
館の中のチマチマした殺人より、
間違いなく大きいので、
大きな事件は解決しないのに、
チマチマした殺人のみ解決するというのでは、
本末転倒で安易であるように感じたのです。
今回はその続編ですが、
前作の設定は踏襲しつつ、
今度は「予言」をテーマにしています。
通常のミステリーでは、
予言というのは基本的にトリックなのですが、
今回はトリックとは思えない予言がバンバン出現し、
ははあ、要するにこれもミステリーと超自然のミックスなのね、
ということが分かります。
今回はラストに、
如何にもミステリー的な捻りがあるので、
前作よりミステリーとしての満足感が高いものになっています。
小さなトリックを積み上げる感じは、
クレイトン・ロースンみたいでしたね。
ただ、矢張り大枠にある謎は、
リアルにせよ超自然的にせよ解決はされないので、
モヤモヤする感じが残ることは同じです。
あと、昔流行った、
大きな木の棒が忽然と現れるという、
マジックネタを利用したトリックがあるのですが、
これはさすがにしょぼくてガッカリしました。
多分マジック好きでない方は、
本文を読まれてもなんのことか分からないと思うのですが、
実際にそうしたネタがあるのです。
ただ、これは出現であって消失の仕掛ではないので、
本文を読む限り成立しないと思いました。
こういうのは僕は嫌いです。
そんな訳で今回もあまり乗らなかったのですが、
一部は脳の老化のせいかなあ、と思うところもあるので、
久しぶりに本家のクイーンでも、
じっくり読んでみようかな、
などと思っています。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
アンソニー・ホロヴィッツ「カササギ殺人事件」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で、
午前中は中村医師が、
午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。
土曜日は趣味の話題です。
今日はこちら。
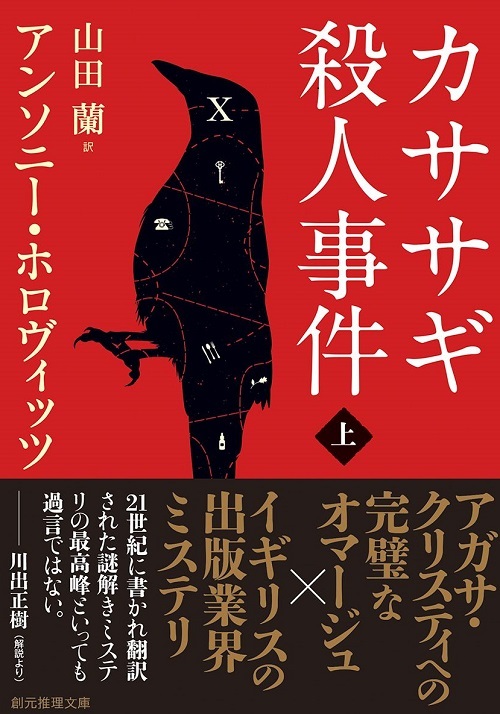
2017年に原書が発売され、
2018年9月に翻訳版が出版されて、
本格翻訳ミステリーとして、
その年随一の評価を得た作品です。
翻訳物の長いミステリというのは、
一気に読まないと面白くないので、
なかなか時間が取れなかったのですが、
この連休に合わせて読了しました。
まあまあかな。
これは入れ子構造になった作品で、
主人公の女性編集者が、
1955年を舞台にした偽古典のようなミステリー小説の発表前の原稿を、
読み始める前からスタートして、
その後にその架空のミステリー小説が丸ごとあり、
その更に後に編集者とミステリー作家を巡る物語に移行して、
リアルと虚構の謎が交錯するという物語になっています。
こうした作品は日本人作家が比較的得意で、
メタミステリなどとも呼ばれ、
「ドグラマグラ」や「虚無への供物」から、
最近の三津田信三さんの諸作まで、
多くの作例があります。
ただ、幻想的で面白い反面、
結局現実と虚構両方の謎がすべて解き明かされる、
ということは稀で、
何処かに常に齟齬はあり、
謎の一部はそのままにされることが通常です。
一方でこの作品は、
それほどお話しとしてとんでもなくなることはなく、
奇想天外でも幻想的でもないので、
その点はやや物足りないのですが、
現実と虚構の2つの謎が完全に解決され、
その両者ともまずまず納得のゆく出来栄えで、
読後にもやもやした感じがないのが一番の特徴です。
虚構のミステリー小説として提示される作品は、
クリスティーとの類似が指摘され、
作者自身もモチーフにしているようなのですが、
どちらかと言えばパトリシア・モイーズや、
ルース・レンデルの本格趣味の傾向の作品に似ています。
まあまあ良くできていますが、
それほどビックリするようなものではないし、
描写もまどろっこしくて繰り返しが多いですよね。
それはリアルの部分の事件にも言えて、
長い手紙や小説の一部を、
長々と引用する部分があるのですが、
結果としてあまり必要性がない感じなので、
結構読んでいてストレスは感じました。
クリスティーを超えた、というような誉め言葉もあるのですが、
果たして何処がどう超えているのでしょうか?
クリスティーはもっと簡潔で凝縮力があり、
幻想味も外連味もありますよね。
この劇中作がクリスティーを超えているとは、
僕にはとても思えませんでした。
総じてとても面白く読みましたが、
正直多くの方が絶賛するほどではないかな、
というのが個人的な印象で、
少なくとも「今世紀最高」とか、
「50年後に残る」というのは、
大袈裟な意見のようにしか感じませんでした。
ミステリー好きにはそこそこお薦めですが、
これなら古典をそのまま読んだ方がいいかも知れません。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で、
午前中は中村医師が、
午後2時以降は石原が外来を担当する予定です。
土曜日は趣味の話題です。
今日はこちら。
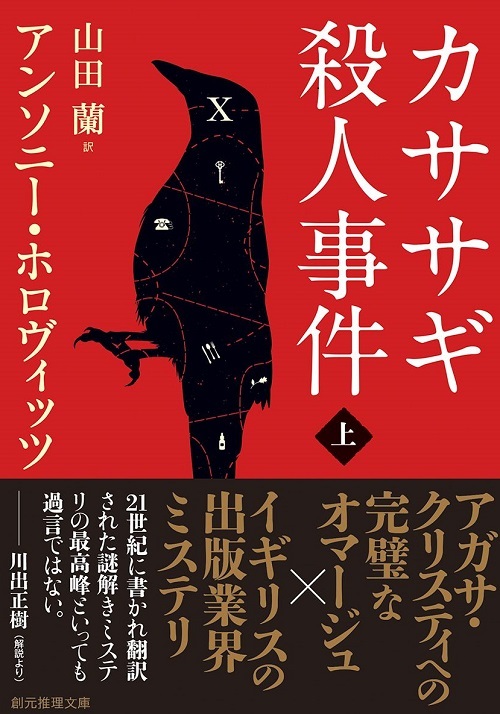
2017年に原書が発売され、
2018年9月に翻訳版が出版されて、
本格翻訳ミステリーとして、
その年随一の評価を得た作品です。
翻訳物の長いミステリというのは、
一気に読まないと面白くないので、
なかなか時間が取れなかったのですが、
この連休に合わせて読了しました。
まあまあかな。
これは入れ子構造になった作品で、
主人公の女性編集者が、
1955年を舞台にした偽古典のようなミステリー小説の発表前の原稿を、
読み始める前からスタートして、
その後にその架空のミステリー小説が丸ごとあり、
その更に後に編集者とミステリー作家を巡る物語に移行して、
リアルと虚構の謎が交錯するという物語になっています。
こうした作品は日本人作家が比較的得意で、
メタミステリなどとも呼ばれ、
「ドグラマグラ」や「虚無への供物」から、
最近の三津田信三さんの諸作まで、
多くの作例があります。
ただ、幻想的で面白い反面、
結局現実と虚構両方の謎がすべて解き明かされる、
ということは稀で、
何処かに常に齟齬はあり、
謎の一部はそのままにされることが通常です。
一方でこの作品は、
それほどお話しとしてとんでもなくなることはなく、
奇想天外でも幻想的でもないので、
その点はやや物足りないのですが、
現実と虚構の2つの謎が完全に解決され、
その両者ともまずまず納得のゆく出来栄えで、
読後にもやもやした感じがないのが一番の特徴です。
虚構のミステリー小説として提示される作品は、
クリスティーとの類似が指摘され、
作者自身もモチーフにしているようなのですが、
どちらかと言えばパトリシア・モイーズや、
ルース・レンデルの本格趣味の傾向の作品に似ています。
まあまあ良くできていますが、
それほどビックリするようなものではないし、
描写もまどろっこしくて繰り返しが多いですよね。
それはリアルの部分の事件にも言えて、
長い手紙や小説の一部を、
長々と引用する部分があるのですが、
結果としてあまり必要性がない感じなので、
結構読んでいてストレスは感じました。
クリスティーを超えた、というような誉め言葉もあるのですが、
果たして何処がどう超えているのでしょうか?
クリスティーはもっと簡潔で凝縮力があり、
幻想味も外連味もありますよね。
この劇中作がクリスティーを超えているとは、
僕にはとても思えませんでした。
総じてとても面白く読みましたが、
正直多くの方が絶賛するほどではないかな、
というのが個人的な印象で、
少なくとも「今世紀最高」とか、
「50年後に残る」というのは、
大袈裟な意見のようにしか感じませんでした。
ミステリー好きにはそこそこお薦めですが、
これなら古典をそのまま読んだ方がいいかも知れません。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
東野圭吾「沈黙のパレード」(ネタバレ注意) [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で、
午前中は石田医師が外来を担当し、
午後2時以降は石原が担当する予定です。
土曜日は趣味の話題です。
今日はこちら。
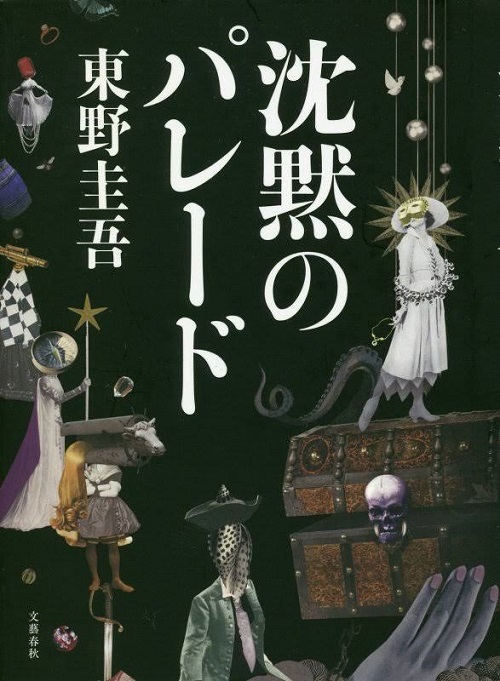
東野圭吾さんのガリレオシリーズの新作長編で、
書き下ろしで昨年刊行されると、
主なミステリーのベストテンで、
1位を獲得するなど抜群の評価を得ている作品です。
ガリレオのシリーズは東野さんの作品の中では、
新本格に近いミステリーのスタイルで、
元々森博嗣さんの作品をパクったような感じがあり、
当初は違和感を感じたのですが、
シリーズ初の長編である「容疑者Xの献身」が直木賞を取り、
その後は独立した特徴も生まれて、
東野さんの本格ミステリー畑の作品としては、
代表的なシリーズとなっています。
その作品のほぼ全てが、
福山雅治さんの主演で映像化されていて、
福山さんが断らなければ、
この新作も同じように映画化される可能性が高いと思います。
短編や中編には、
オヤオヤと感じるようなものも多いのですが、
これまでに刊行された長編は、
「容疑者Xの献身」「聖女の救済」「真夏の方程式」と、
いずれも力の入った優れたミステリーになっていて、
東野さんの多くの作品の中でも読み応えがありますし、
東野さん自身も力を入れて書いていることが分かります。
今回の作品も、如何にもガリレオシリーズという感じで、
舞台を用意して主人公の名探偵をその場に居合わせ、
その目の前で不可解な事件を起こすという構成は、
クリスティーやカーの黄金時代の本格ミステリーの構成そのものです。
クリスティーやカー、
スラデックなどの古典ミステリーのトリックを、
一部明かしているようなところがあるので、
「オリエント急行殺人事件」や「ユダの窓」、
「見えないグリーン」については、
是非原典を読んでから、
この作品を読まれることをお薦めします。
つまり、割合とミステリーマニア向けに、
書いているようなところのある作品なのです。
またガリレオシリーズの旧作や新参者シリーズの作品も、
先に読んでおいた方が良いと思います。
東野さんは結構過去作のトリックや設定を、
流用して再構成することが多いからです。
以下勿論ネタバレはしませんが、
内容を類推出来るような表現がありますので、
先入観なくこの作品をお読みになりたい方は、
本作読了後に以下はお読み下さい。
よろしいでしょうか。
それでは続けます。
リーダビリティもクオリティも高いので、
読んでガッカリするような作品ではありません。
ただ、個人的には過去作の焼き直し的な趣向が多く、
目新しさはないな、というのが正直なところです。
全体の構成は「真夏の方程式」に非常に良く似ていて、
主人公の関わり方もそっくりなのですが、
比較すると「真夏の方程式」の方が、
その切なさや余韻の面で、
優れていたように思います。
最後のひねりは、
ちょっとわざとらしすぎるという気がします。
それに最終的な解決は、
ほぼ想像に近い推測で、
何ら根拠はありませんよね。
犯人でありながら司法で裁かれない人物の設定には、
「検察側の罪人」の影響が、
かなりあるのではないかと感じました。
事件自体も全員のアリバイが、
それほどしっかり確認されるという感じではないので、
事件自体のワクワク感も乏しいように思いました。
パレードの活用のされ方も、
意外に詰まらないですよね。
もう一工夫欲しかったと思います。
計画犯罪が途中でアクシデントがあることで、
より不可解な事件になるというのは、
クイーンのスタイルで、
日本では有栖川有栖さんなどが得意とするところですが、
こういうのは東野さんはあまり上手ではないと思います。
ある人物の設定などは、
切なくて東野さん好みなのですが、
これもある旧作の焼き直しで、
旧作の方がインパクトは大きかったと思いますし、
過去作を読んでいると、
何となく構造は分かってしまって、
それほど驚けないのもつらいところです。
そんな訳で東野さんの本格ミステリーとしては、
高いレベルの水準作という感じで、
あまり飛び抜けた印象や、
独自性は感じにくいように思いました。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は土曜日で、
午前中は石田医師が外来を担当し、
午後2時以降は石原が担当する予定です。
土曜日は趣味の話題です。
今日はこちら。
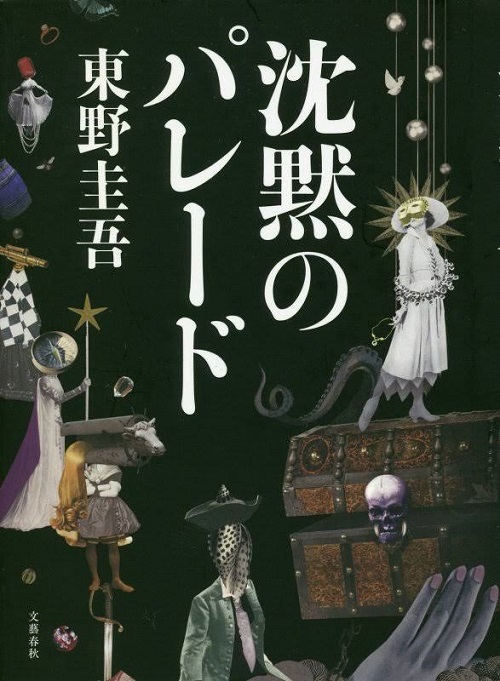
東野圭吾さんのガリレオシリーズの新作長編で、
書き下ろしで昨年刊行されると、
主なミステリーのベストテンで、
1位を獲得するなど抜群の評価を得ている作品です。
ガリレオのシリーズは東野さんの作品の中では、
新本格に近いミステリーのスタイルで、
元々森博嗣さんの作品をパクったような感じがあり、
当初は違和感を感じたのですが、
シリーズ初の長編である「容疑者Xの献身」が直木賞を取り、
その後は独立した特徴も生まれて、
東野さんの本格ミステリー畑の作品としては、
代表的なシリーズとなっています。
その作品のほぼ全てが、
福山雅治さんの主演で映像化されていて、
福山さんが断らなければ、
この新作も同じように映画化される可能性が高いと思います。
短編や中編には、
オヤオヤと感じるようなものも多いのですが、
これまでに刊行された長編は、
「容疑者Xの献身」「聖女の救済」「真夏の方程式」と、
いずれも力の入った優れたミステリーになっていて、
東野さんの多くの作品の中でも読み応えがありますし、
東野さん自身も力を入れて書いていることが分かります。
今回の作品も、如何にもガリレオシリーズという感じで、
舞台を用意して主人公の名探偵をその場に居合わせ、
その目の前で不可解な事件を起こすという構成は、
クリスティーやカーの黄金時代の本格ミステリーの構成そのものです。
クリスティーやカー、
スラデックなどの古典ミステリーのトリックを、
一部明かしているようなところがあるので、
「オリエント急行殺人事件」や「ユダの窓」、
「見えないグリーン」については、
是非原典を読んでから、
この作品を読まれることをお薦めします。
つまり、割合とミステリーマニア向けに、
書いているようなところのある作品なのです。
またガリレオシリーズの旧作や新参者シリーズの作品も、
先に読んでおいた方が良いと思います。
東野さんは結構過去作のトリックや設定を、
流用して再構成することが多いからです。
以下勿論ネタバレはしませんが、
内容を類推出来るような表現がありますので、
先入観なくこの作品をお読みになりたい方は、
本作読了後に以下はお読み下さい。
よろしいでしょうか。
それでは続けます。
リーダビリティもクオリティも高いので、
読んでガッカリするような作品ではありません。
ただ、個人的には過去作の焼き直し的な趣向が多く、
目新しさはないな、というのが正直なところです。
全体の構成は「真夏の方程式」に非常に良く似ていて、
主人公の関わり方もそっくりなのですが、
比較すると「真夏の方程式」の方が、
その切なさや余韻の面で、
優れていたように思います。
最後のひねりは、
ちょっとわざとらしすぎるという気がします。
それに最終的な解決は、
ほぼ想像に近い推測で、
何ら根拠はありませんよね。
犯人でありながら司法で裁かれない人物の設定には、
「検察側の罪人」の影響が、
かなりあるのではないかと感じました。
事件自体も全員のアリバイが、
それほどしっかり確認されるという感じではないので、
事件自体のワクワク感も乏しいように思いました。
パレードの活用のされ方も、
意外に詰まらないですよね。
もう一工夫欲しかったと思います。
計画犯罪が途中でアクシデントがあることで、
より不可解な事件になるというのは、
クイーンのスタイルで、
日本では有栖川有栖さんなどが得意とするところですが、
こういうのは東野さんはあまり上手ではないと思います。
ある人物の設定などは、
切なくて東野さん好みなのですが、
これもある旧作の焼き直しで、
旧作の方がインパクトは大きかったと思いますし、
過去作を読んでいると、
何となく構造は分かってしまって、
それほど驚けないのもつらいところです。
そんな訳で東野さんの本格ミステリーとしては、
高いレベルの水準作という感じで、
あまり飛び抜けた印象や、
独自性は感じにくいように思いました。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
東野圭吾「人魚の眠る家」 [ミステリー]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は祝日でクリニックは休診です。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。
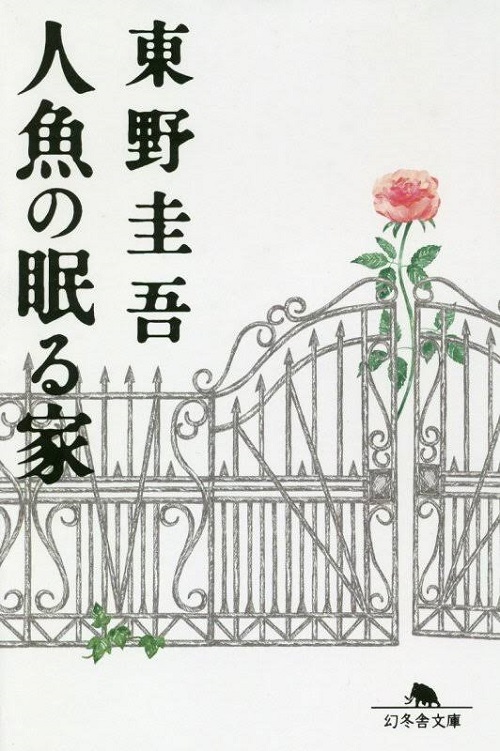
東野圭吾さんはまだ地味なミステリー作家であった時代の、
「鳥人計画」や「ブルータスの心臓」、
屈折した青春ミステリーの「魔球」などが好きで、
この辺りはまだブレイクする前に、
まとめ読みをしています。
その後はしばらくご無沙汰だったのですが、
「秘密」にビックリしてとてもとても感動して、
読み終えた時の二子玉川のケンタッキーの店内の雰囲気や、
曇天の夕暮れの空の色、寒さの感触まで今もリアルに覚えています。
それからの活躍は皆さんご存じの通りで、
あまりに多作過ぎるので、
作品の出来不出来が激しくて、
オヤオヤという感じのものも多いのですが、
語り口は極めて巧みでスイスイ抵抗なく読めてしまうので、
ちょっと時間が空いて読書という時には、
安心して手が伸ばせるので読んでしまいます。
個人的には「秘密」が抜群で、
次に「手紙」が凄いと思いますが、
前述の初期作も良いと思いますし、
最近では映画化もされた(最近はほとんどされていますが)
「祈りの幕が下りる時」が、
清張さんの「砂の器」を換骨奪胎して、
ミステリーと人間ドラマの案配が巧みな快作でした。
森博嗣さんのパクリとして始まったガリレオシリーズも、
長編はどれも粒揃いで読み応えがあります。
東野さんは端的に言えば「理系脳の悪意の人」で、
相当歪んだ倫理観をお持ちだと思います。
(悪口ではありません)
初期作ではそれが生々しい感じで出ていて、
そのために読者を選ぶ感じがあったのですが、
「秘密」はその屈折した人間観の奥底にある、
秘められた無垢な情念のようなものが、
初めて露になった観じがあって、
それ以降は理知と感情との相克が、
物語の骨格を作るようになりました。
初期は単純な勧善懲悪的なストーリーは、
決して書かなかったのですが、
ベストセラー作家となって以降は、
そうした穏当な作品がむしろ多くなって行きます。
ただ、そうなっても人間や社会を見据える視線は、
独特で屈折したダークな面を保っています。
この「人魚の眠る家」は映画化に併せて読んだのですが、
まだ時間がなくて映画は観ていません。
多分見ないままに終わる可能性が高そうです。
この作品は前半はなかなか読み応えがありました。
脳死と臓器移植の問題を扱っているのですが、
東野さんの見方は例によってかなりシニカルで、
その情緒を廃した怜悧な感じが作者ならではという感じがします。
2つの異なった考え方の対立を、
論理で徹底して詰める辺りが凄いですね。
途中にひねりを入れて、
アイラ・レヴィンの「死の接吻」を思わせる、
予想の付かない展開にもワクワクします。
この辺りワンテーマを掘り下げるという点では、
「手紙」を彷彿とさせますし、
横隔膜ペーシングや筋肉への電気刺激など、
今ある技術を利用して、
現実より少し進んだ絵を描いてみせるという、
SFにはならない科学応用というのも、
「鳥人計画」辺りに近いスタンスです。
ただ、クライマックスからラストに掛けては、
子供をだしにしたお涙頂戴的な感じになり、
ラストは如何にも予定調和的なもので、
夢と子供で決着させるという安易さには、
ちょっと落胆する感じがありました。
昔のもっと悪意に満ちた東野さんであれば、
母親の行為はもっととんでもない方向に、
シフトしたのではないかと思いますし、
万人向けで現実の医療にも寛容なラストなど、
決して選択はしなかったのではないか、
というように思いました。
映画は観ていませんが、
この原作通りにするのだとすると、
おそらく尻すぼみの印象になるように推測され、
何となく足が向かないというのが正直なところです。
映画が観られましたら、また感想は書きたいと思います。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は祝日でクリニックは休診です。
休みの日は趣味の話題です。
今日はこちら。
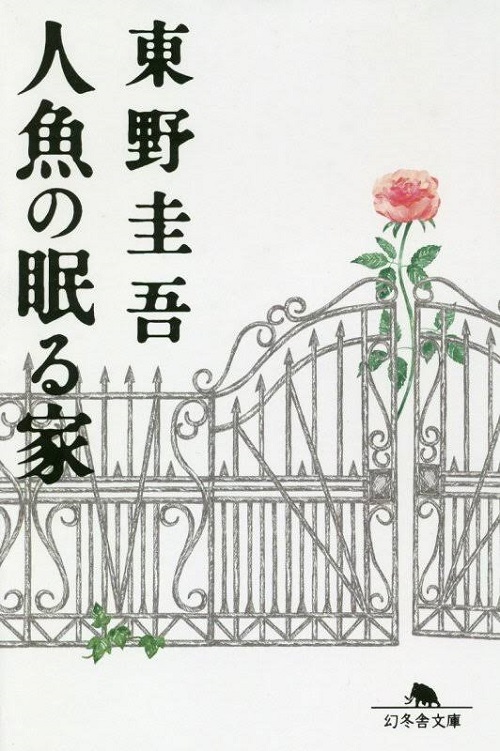
東野圭吾さんはまだ地味なミステリー作家であった時代の、
「鳥人計画」や「ブルータスの心臓」、
屈折した青春ミステリーの「魔球」などが好きで、
この辺りはまだブレイクする前に、
まとめ読みをしています。
その後はしばらくご無沙汰だったのですが、
「秘密」にビックリしてとてもとても感動して、
読み終えた時の二子玉川のケンタッキーの店内の雰囲気や、
曇天の夕暮れの空の色、寒さの感触まで今もリアルに覚えています。
それからの活躍は皆さんご存じの通りで、
あまりに多作過ぎるので、
作品の出来不出来が激しくて、
オヤオヤという感じのものも多いのですが、
語り口は極めて巧みでスイスイ抵抗なく読めてしまうので、
ちょっと時間が空いて読書という時には、
安心して手が伸ばせるので読んでしまいます。
個人的には「秘密」が抜群で、
次に「手紙」が凄いと思いますが、
前述の初期作も良いと思いますし、
最近では映画化もされた(最近はほとんどされていますが)
「祈りの幕が下りる時」が、
清張さんの「砂の器」を換骨奪胎して、
ミステリーと人間ドラマの案配が巧みな快作でした。
森博嗣さんのパクリとして始まったガリレオシリーズも、
長編はどれも粒揃いで読み応えがあります。
東野さんは端的に言えば「理系脳の悪意の人」で、
相当歪んだ倫理観をお持ちだと思います。
(悪口ではありません)
初期作ではそれが生々しい感じで出ていて、
そのために読者を選ぶ感じがあったのですが、
「秘密」はその屈折した人間観の奥底にある、
秘められた無垢な情念のようなものが、
初めて露になった観じがあって、
それ以降は理知と感情との相克が、
物語の骨格を作るようになりました。
初期は単純な勧善懲悪的なストーリーは、
決して書かなかったのですが、
ベストセラー作家となって以降は、
そうした穏当な作品がむしろ多くなって行きます。
ただ、そうなっても人間や社会を見据える視線は、
独特で屈折したダークな面を保っています。
この「人魚の眠る家」は映画化に併せて読んだのですが、
まだ時間がなくて映画は観ていません。
多分見ないままに終わる可能性が高そうです。
この作品は前半はなかなか読み応えがありました。
脳死と臓器移植の問題を扱っているのですが、
東野さんの見方は例によってかなりシニカルで、
その情緒を廃した怜悧な感じが作者ならではという感じがします。
2つの異なった考え方の対立を、
論理で徹底して詰める辺りが凄いですね。
途中にひねりを入れて、
アイラ・レヴィンの「死の接吻」を思わせる、
予想の付かない展開にもワクワクします。
この辺りワンテーマを掘り下げるという点では、
「手紙」を彷彿とさせますし、
横隔膜ペーシングや筋肉への電気刺激など、
今ある技術を利用して、
現実より少し進んだ絵を描いてみせるという、
SFにはならない科学応用というのも、
「鳥人計画」辺りに近いスタンスです。
ただ、クライマックスからラストに掛けては、
子供をだしにしたお涙頂戴的な感じになり、
ラストは如何にも予定調和的なもので、
夢と子供で決着させるという安易さには、
ちょっと落胆する感じがありました。
昔のもっと悪意に満ちた東野さんであれば、
母親の行為はもっととんでもない方向に、
シフトしたのではないかと思いますし、
万人向けで現実の医療にも寛容なラストなど、
決して選択はしなかったのではないか、
というように思いました。
映画は観ていませんが、
この原作通りにするのだとすると、
おそらく尻すぼみの印象になるように推測され、
何となく足が向かないというのが正直なところです。
映画が観られましたら、また感想は書きたいと思います。
それでは今日はこのくらいで。
皆さんも良い休日をお過ごし下さい。
石原がお送りしました。



