慢性難治性咳嗽と脳機能との関係性 [医療のトピック]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は午前午後ともいつも通りの診療になります。
今日は誤診や診療の過誤なく、
1日を終えることが出来るでしょうか?
何かを求めてお出でになった患者さんに、
それを提供することが出来るでしょうか?
その意味でのミスマッチを最小限度に抑えることが出来るでしょうか?
発熱外来以降、患者さんには怒られ、
スタッフは態度が悪いと罵倒され、
行政には翻弄され、大病院には虫けらの如く扱われ、
近隣や同じビルの方には煙たがられ、
多分診療を始めてから最も不毛で空しい日々が続いていますが、
それでも、これまではこれまでとして、
未来は決まっているものではないのですから、
少なくとも今日1日の診療においては、
完璧に近いものを目指しつつ、
今日出来る精いっぱい(根本宗子さん的表現です)を心に誓って、
今から診療に当たろうとは思っています。
それでは今日の話題です。
今日はこちら。
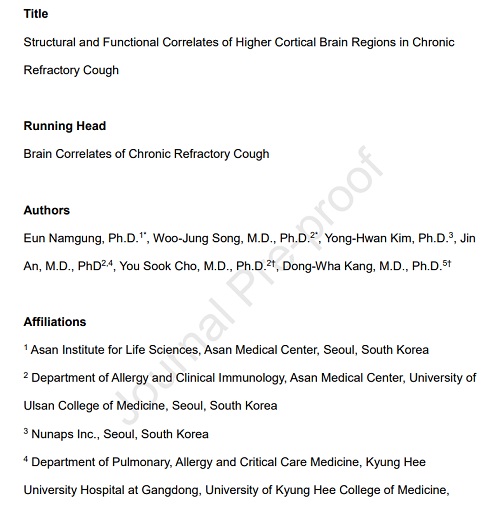
Chest Journal誌に、
2022年4月29日ウェブ掲載された、
慢性の咳症状に対する脳の関与を検証した論文です。
長引く咳というのは非常に一般的な症状で、
8週間以上持続する咳を慢性咳嗽と言いますが、
その頻度は人口の5から10%に達するという報告もあるほどです。
咳というのは、
気道に侵入した異物を速やかに排出するため、
延髄の咳中枢からの指令により、
声門の閉鎖や呼吸筋の収縮などが連動して起こる一種の反射で、
慢性の咳の多くは、
何らかの原因によりその反射が敏感になり、
少しの刺激、場合によっては刺激がないのに、
咳反射が起こってしまうことがその本質ではないかと考えられています。
その原因の1つは、
気道にある咳受容体が敏感になることで、
アレルギー性の咳と呼ばれるものは、
気道のアレルギー性の炎症が起こって、
それが咳受容体の感受性を亢進させることによって起こる、
というように説明されます。
そして、それ以外に原因として考えられるのが、
咳中枢やそれより上位の大脳皮質中枢の関与です。
つまり、咳は脳から来ているのではないか、
という考え方です。
確かに不安による発作の症状の1つとして、
咳発作が見られることがあります。
また、慢性の咳というのは非常にストレスなものですから、
それが不安を高め、結果として咳の閾値を低下させる、
というメカニズムも推測されます。
ただ、こうした咳と脳機能との関連の詳細は、
これまでにあまり分かっていませんでした。
今回の研究は韓国において、
慢性難治性咳嗽の患者15名と、
年齢などをマッチングさせたボランティア15名に、
機能性MRI検査を施行し、
脳の形態や機能と慢性咳嗽との関連を比較検証しているものです。
その結果、
慢性咳嗽患者は左前頭葉の灰白質容積が減少しており、
左前頭葉と頭頂葉との機能的な結合が強い傾向が認められました。
この左前頭葉の萎縮は咳の持続期間が長いほど強く、
左前頭葉と頭頂葉との結合の強さは、
咳が生活に与える影響の強さと関連していました。
このように、
慢性の咳は脳の形態や機能に関連があり、
それが咳の原因ではないにしても、
その持続や増悪の要因となっていると思われます。
従って、慢性難治性咳嗽の治療には、
心理療法的なアプローチや心療内科的なアプローチが、
今後は重要となると共に、
脳機能の回復に繋がるような、
治療についても検討される必要がありそうです。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は午前午後ともいつも通りの診療になります。
今日は誤診や診療の過誤なく、
1日を終えることが出来るでしょうか?
何かを求めてお出でになった患者さんに、
それを提供することが出来るでしょうか?
その意味でのミスマッチを最小限度に抑えることが出来るでしょうか?
発熱外来以降、患者さんには怒られ、
スタッフは態度が悪いと罵倒され、
行政には翻弄され、大病院には虫けらの如く扱われ、
近隣や同じビルの方には煙たがられ、
多分診療を始めてから最も不毛で空しい日々が続いていますが、
それでも、これまではこれまでとして、
未来は決まっているものではないのですから、
少なくとも今日1日の診療においては、
完璧に近いものを目指しつつ、
今日出来る精いっぱい(根本宗子さん的表現です)を心に誓って、
今から診療に当たろうとは思っています。
それでは今日の話題です。
今日はこちら。
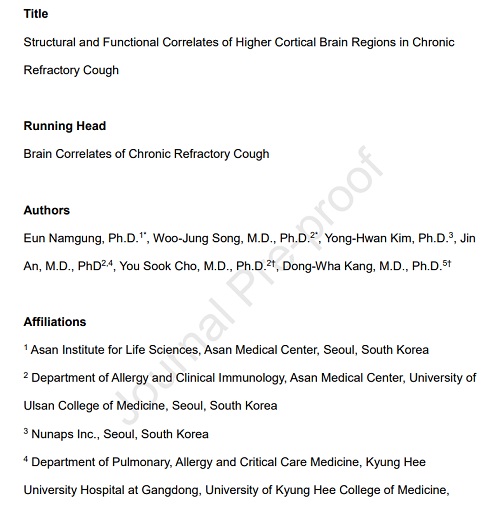
Chest Journal誌に、
2022年4月29日ウェブ掲載された、
慢性の咳症状に対する脳の関与を検証した論文です。
長引く咳というのは非常に一般的な症状で、
8週間以上持続する咳を慢性咳嗽と言いますが、
その頻度は人口の5から10%に達するという報告もあるほどです。
咳というのは、
気道に侵入した異物を速やかに排出するため、
延髄の咳中枢からの指令により、
声門の閉鎖や呼吸筋の収縮などが連動して起こる一種の反射で、
慢性の咳の多くは、
何らかの原因によりその反射が敏感になり、
少しの刺激、場合によっては刺激がないのに、
咳反射が起こってしまうことがその本質ではないかと考えられています。
その原因の1つは、
気道にある咳受容体が敏感になることで、
アレルギー性の咳と呼ばれるものは、
気道のアレルギー性の炎症が起こって、
それが咳受容体の感受性を亢進させることによって起こる、
というように説明されます。
そして、それ以外に原因として考えられるのが、
咳中枢やそれより上位の大脳皮質中枢の関与です。
つまり、咳は脳から来ているのではないか、
という考え方です。
確かに不安による発作の症状の1つとして、
咳発作が見られることがあります。
また、慢性の咳というのは非常にストレスなものですから、
それが不安を高め、結果として咳の閾値を低下させる、
というメカニズムも推測されます。
ただ、こうした咳と脳機能との関連の詳細は、
これまでにあまり分かっていませんでした。
今回の研究は韓国において、
慢性難治性咳嗽の患者15名と、
年齢などをマッチングさせたボランティア15名に、
機能性MRI検査を施行し、
脳の形態や機能と慢性咳嗽との関連を比較検証しているものです。
その結果、
慢性咳嗽患者は左前頭葉の灰白質容積が減少しており、
左前頭葉と頭頂葉との機能的な結合が強い傾向が認められました。
この左前頭葉の萎縮は咳の持続期間が長いほど強く、
左前頭葉と頭頂葉との結合の強さは、
咳が生活に与える影響の強さと関連していました。
このように、
慢性の咳は脳の形態や機能に関連があり、
それが咳の原因ではないにしても、
その持続や増悪の要因となっていると思われます。
従って、慢性難治性咳嗽の治療には、
心理療法的なアプローチや心療内科的なアプローチが、
今後は重要となると共に、
脳機能の回復に繋がるような、
治療についても検討される必要がありそうです。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。



