抗コリン剤の長期使用と認知症リスク [医療のトピック]
こんにちは。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は午前午後ともいつも通りの診療になります。
それでは今日の話題です。
今日はこちら。
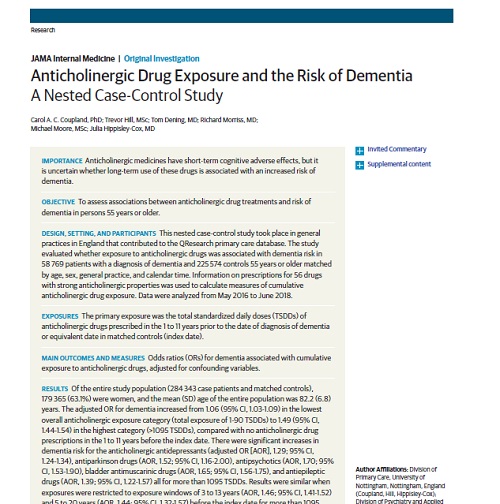
2019年のJAMA Internal Medicine誌に掲載された、
抗コリン作用という、
色々な診療科で使用される薬が持っている作用による、
認知症リスクについての論文です。
この問題はこれまでにも何度か取り上げています。
今回はこれまでの経緯を含めてまとめておきたいと思います。
抗コリン作用と言うのは、
副交感神経に代表される、
アセチルコリン作動性神経の働きを抑えるというもので、
非常に多くの薬剤がこの作用を持っています。
その中には抗コリン作用そのものが、
薬の効果であるものもありますし、
副作用として抗コリン作用を持つものもあります。
アセチルコリン作動性神経により、
胃や気管支、膀胱などの平滑筋は収縮しますから、
胃痙攣を抑える目的で使用されたり、
気管支拡張剤として、
また過活動性膀胱の治療薬として使用されます。
パーキンソン症候群の補助的な治療薬として、
使用されることもあります。
その一方で、
鼻水や痒みを止める抗ヒスタミン剤や、
抗うつ剤や抗精神薬は、
副作用としての抗コリン作用を持っています。
この抗コリン作用は基本的に末梢神経のものですが、
脳への作用も皆無ではありません。
一方で認知症では脳のアセチルコリン作動性神経の障害が、
早期に起こると考えられています。
そのために、
現在認知症の進行抑制目的で使用されている、
ドネペジル(商品名アリセプトなど)は、
脳内のアセチルコリンを増やす作用の薬です。
抗コリン剤はアセチルコリン作動性神経を抑制する薬ですから、
これがそのまま脳に働けば、
脳のアセチルコリン作動性神経の働きを弱め、
認知症のような症状を出すであろうことは、
当然想定されるところです。
実際に高齢者に抗コリン剤を使用することにより、
せん妄状態や、記憶障害や注意力の障害など、
認知症様の症状が急性に見られることは、
良く知られた事実です。
通常こうした急性の症状は、
薬剤の中止により回復する、
一時的なものと考えられています。
しかし、
高齢者が長期間こうした薬剤を使用している場合はどうでしょうか?
それが認知症の発症に繋がるようなことはないのでしょうか?
この点については、
あまり長期間の観察を行なったようなデータが、
これまで存在していませんでしたが、
2015年1月のJAMA Internal Medicine誌に、
アメリカにおける、
高齢者の大規模な健康調査のデータを活用して、
抗コリン剤の長期処方と、
認知症の発症との関連を検証した論文が掲載されました。
これは発表の時期にブログ記事にしています。
65歳以上の認知症のない高齢者3434名を登録し、
平均で7.3年間の経過観察を施行したデータを解析したところ、
65歳以上の高齢者が、
3年以上常用量の抗コリン作用のある薬を使用すると、
その薬の種別に関わらず、
最大で1.5倍程度の
認知症のリスクの増加が生じる可能性がある、
という結果が得られています。
ただ、このデータにおいては、
個別の抗コリン作用のある薬の種別と、
認知症リスクとの関連は明らかではありません。
通常に考えると、
泌尿器科などで高齢者に長期使用が常態化している、
過活動性膀胱の治療薬などは、
その脳への作用は限定的であるように、
薬の添付文書などを見る限りはそう思えます。
しかし、それは本当に正しい考え方なのでしょうか?
これまでの文献上での検討から、
抗コリン作用を持つ薬の脳への影響の強さは、
ACBスケールという指標により、分類されています。
これによると、
抗コリン作用自体はあることが確認されているものの、
それが認知機能に悪影響を与えたという報告のない薬が、
ACBスコアで1点、
脳への抗コリン作用が臨床的に確認されている薬が、2点、
そして更にせん妄などの発生が報告されている薬が、3点、
それ以外の薬は0点となっています。
具体的には三環系の抗うつ剤やパロキセチンなどのSSRIの大部分、
胃痛などを抑える、アトロピンやスコポラミン、
過活動性膀胱の治療薬である、
トルテロジン(デトルシトール)やオキシブチニン(ポラキス)、
ソリフェナシン(ベシケア)、
オランザピンなどの抗精神病薬、
ヒドロキシジン(アタラックスP)やプロメタジンなどの、
第一世代抗ヒスタミン剤などが、
このACBスコア3点となっています。
そこでイギリスのプライマリケアのデータベースを元にして、
40770名の認知症の患者さんを、
283933名のコントロールと比較して、
抗コリン作用のある薬剤の使用歴と、
認知症のリスクとの関連を検証した研究が行われ、
2018年5月のBritish Medical Journal誌に発表されました。
これも同時期にブログ記事にしています。
その結果を掻い摘まんで言うと、
ACBスコア3点の薬剤の使用により、
他のリスクを補正した結果として、
認知症のリスクは1.11倍(95%CI; 1.08から1.14)
有意に増加していました。
ACBスコア3点以外の薬剤のリスクは有意なものではなく、
3点の薬の中でも、
抗うつ剤、パーキンソン病治療薬、泌尿器科治療薬のリスクが、
より高いものとなっていました。
こうした薬剤に関しては、
認知症と診断される15から20年前の処方についても、
関連が認められました。
今回の研究は2018年論文と同じく、
イギリスのプライマリケアのデータベースを元にしたものですが、
55歳以上で認知症と診断された58769名を、
年齢性別などをマッチさせた、
225574名のコントロールと比較して、
抗コリン作用を持つ薬剤の認知症診断以前1から11年の使用と、
認知症発症リスクとの関連を検証したもので、
これまでで最も大規模な疫学研究です。
その結果、
認知症と診断する前1から11年に、
抗コリン剤を通常の使用量に換算して、
累積で1095日以上内服していると、
内服していない場合と比較して、
認知症の発症リスクは49%(95%CI: 1.44から1.54)、
有意に増加していて、
これは累積で1から90日の使用においても、
6%(95%CI: 1.03から1.09)有意に増加していました。
薬剤毎の解析においては、
抗うつ剤と過活動性膀胱の治療薬、
抗精神病薬や抗痙攣剤のリスクが高く、
抗ヒスタミン剤や筋弛緩剤、
気管支拡張剤や胃の鎮痙剤などについては、
単独で有意な認知症リスクの増加は認められませんでした。
この点は以前の論文とは少し結果が異なります。
この抗コリン剤の使用継続による認知症リスクは、
特に80歳以前で診断された認知症で高く、
アルツハイマー型認知症より脳血管性認知症でより高い、
という特徴がありました。
トータルにみて全ての認知症の発症において、
その診断前1から11年における抗コリン剤の使用は、
その10.3%に影響をしていると計算されました。
今回の結果はこれまでのデータを更に補強するもので、
認知症の1割は抗コリン剤が影響している可能性がある、
という結果はかなり重い意味を持つもので、
少なくとも65歳以上での長期の抗コリン剤の使用については、
これまで以上に慎重に考える必要がありそうです。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
北品川藤クリニックの石原です。
今日は午前午後ともいつも通りの診療になります。
それでは今日の話題です。
今日はこちら。
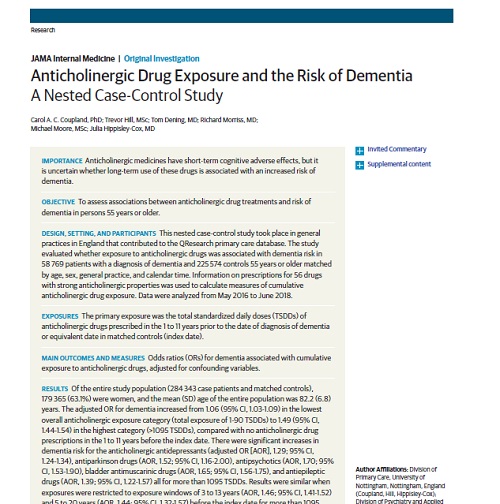
2019年のJAMA Internal Medicine誌に掲載された、
抗コリン作用という、
色々な診療科で使用される薬が持っている作用による、
認知症リスクについての論文です。
この問題はこれまでにも何度か取り上げています。
今回はこれまでの経緯を含めてまとめておきたいと思います。
抗コリン作用と言うのは、
副交感神経に代表される、
アセチルコリン作動性神経の働きを抑えるというもので、
非常に多くの薬剤がこの作用を持っています。
その中には抗コリン作用そのものが、
薬の効果であるものもありますし、
副作用として抗コリン作用を持つものもあります。
アセチルコリン作動性神経により、
胃や気管支、膀胱などの平滑筋は収縮しますから、
胃痙攣を抑える目的で使用されたり、
気管支拡張剤として、
また過活動性膀胱の治療薬として使用されます。
パーキンソン症候群の補助的な治療薬として、
使用されることもあります。
その一方で、
鼻水や痒みを止める抗ヒスタミン剤や、
抗うつ剤や抗精神薬は、
副作用としての抗コリン作用を持っています。
この抗コリン作用は基本的に末梢神経のものですが、
脳への作用も皆無ではありません。
一方で認知症では脳のアセチルコリン作動性神経の障害が、
早期に起こると考えられています。
そのために、
現在認知症の進行抑制目的で使用されている、
ドネペジル(商品名アリセプトなど)は、
脳内のアセチルコリンを増やす作用の薬です。
抗コリン剤はアセチルコリン作動性神経を抑制する薬ですから、
これがそのまま脳に働けば、
脳のアセチルコリン作動性神経の働きを弱め、
認知症のような症状を出すであろうことは、
当然想定されるところです。
実際に高齢者に抗コリン剤を使用することにより、
せん妄状態や、記憶障害や注意力の障害など、
認知症様の症状が急性に見られることは、
良く知られた事実です。
通常こうした急性の症状は、
薬剤の中止により回復する、
一時的なものと考えられています。
しかし、
高齢者が長期間こうした薬剤を使用している場合はどうでしょうか?
それが認知症の発症に繋がるようなことはないのでしょうか?
この点については、
あまり長期間の観察を行なったようなデータが、
これまで存在していませんでしたが、
2015年1月のJAMA Internal Medicine誌に、
アメリカにおける、
高齢者の大規模な健康調査のデータを活用して、
抗コリン剤の長期処方と、
認知症の発症との関連を検証した論文が掲載されました。
これは発表の時期にブログ記事にしています。
65歳以上の認知症のない高齢者3434名を登録し、
平均で7.3年間の経過観察を施行したデータを解析したところ、
65歳以上の高齢者が、
3年以上常用量の抗コリン作用のある薬を使用すると、
その薬の種別に関わらず、
最大で1.5倍程度の
認知症のリスクの増加が生じる可能性がある、
という結果が得られています。
ただ、このデータにおいては、
個別の抗コリン作用のある薬の種別と、
認知症リスクとの関連は明らかではありません。
通常に考えると、
泌尿器科などで高齢者に長期使用が常態化している、
過活動性膀胱の治療薬などは、
その脳への作用は限定的であるように、
薬の添付文書などを見る限りはそう思えます。
しかし、それは本当に正しい考え方なのでしょうか?
これまでの文献上での検討から、
抗コリン作用を持つ薬の脳への影響の強さは、
ACBスケールという指標により、分類されています。
これによると、
抗コリン作用自体はあることが確認されているものの、
それが認知機能に悪影響を与えたという報告のない薬が、
ACBスコアで1点、
脳への抗コリン作用が臨床的に確認されている薬が、2点、
そして更にせん妄などの発生が報告されている薬が、3点、
それ以外の薬は0点となっています。
具体的には三環系の抗うつ剤やパロキセチンなどのSSRIの大部分、
胃痛などを抑える、アトロピンやスコポラミン、
過活動性膀胱の治療薬である、
トルテロジン(デトルシトール)やオキシブチニン(ポラキス)、
ソリフェナシン(ベシケア)、
オランザピンなどの抗精神病薬、
ヒドロキシジン(アタラックスP)やプロメタジンなどの、
第一世代抗ヒスタミン剤などが、
このACBスコア3点となっています。
そこでイギリスのプライマリケアのデータベースを元にして、
40770名の認知症の患者さんを、
283933名のコントロールと比較して、
抗コリン作用のある薬剤の使用歴と、
認知症のリスクとの関連を検証した研究が行われ、
2018年5月のBritish Medical Journal誌に発表されました。
これも同時期にブログ記事にしています。
その結果を掻い摘まんで言うと、
ACBスコア3点の薬剤の使用により、
他のリスクを補正した結果として、
認知症のリスクは1.11倍(95%CI; 1.08から1.14)
有意に増加していました。
ACBスコア3点以外の薬剤のリスクは有意なものではなく、
3点の薬の中でも、
抗うつ剤、パーキンソン病治療薬、泌尿器科治療薬のリスクが、
より高いものとなっていました。
こうした薬剤に関しては、
認知症と診断される15から20年前の処方についても、
関連が認められました。
今回の研究は2018年論文と同じく、
イギリスのプライマリケアのデータベースを元にしたものですが、
55歳以上で認知症と診断された58769名を、
年齢性別などをマッチさせた、
225574名のコントロールと比較して、
抗コリン作用を持つ薬剤の認知症診断以前1から11年の使用と、
認知症発症リスクとの関連を検証したもので、
これまでで最も大規模な疫学研究です。
その結果、
認知症と診断する前1から11年に、
抗コリン剤を通常の使用量に換算して、
累積で1095日以上内服していると、
内服していない場合と比較して、
認知症の発症リスクは49%(95%CI: 1.44から1.54)、
有意に増加していて、
これは累積で1から90日の使用においても、
6%(95%CI: 1.03から1.09)有意に増加していました。
薬剤毎の解析においては、
抗うつ剤と過活動性膀胱の治療薬、
抗精神病薬や抗痙攣剤のリスクが高く、
抗ヒスタミン剤や筋弛緩剤、
気管支拡張剤や胃の鎮痙剤などについては、
単独で有意な認知症リスクの増加は認められませんでした。
この点は以前の論文とは少し結果が異なります。
この抗コリン剤の使用継続による認知症リスクは、
特に80歳以前で診断された認知症で高く、
アルツハイマー型認知症より脳血管性認知症でより高い、
という特徴がありました。
トータルにみて全ての認知症の発症において、
その診断前1から11年における抗コリン剤の使用は、
その10.3%に影響をしていると計算されました。
今回の結果はこれまでのデータを更に補強するもので、
認知症の1割は抗コリン剤が影響している可能性がある、
という結果はかなり重い意味を持つもので、
少なくとも65歳以上での長期の抗コリン剤の使用については、
これまで以上に慎重に考える必要がありそうです。
それでは今日はこのくらいで。
今日が皆さんにとっていい日でありますように。
石原がお送りしました。
2019-07-04 06:13
nice!(7)
コメント(0)




コメント 0